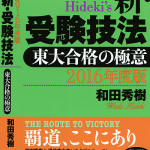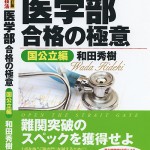生徒と教師が共に学習計画を立て、何をどう学ぶかを決めていく。人生や社会の課題解決を見据えた学び方の新たなスタンダード。
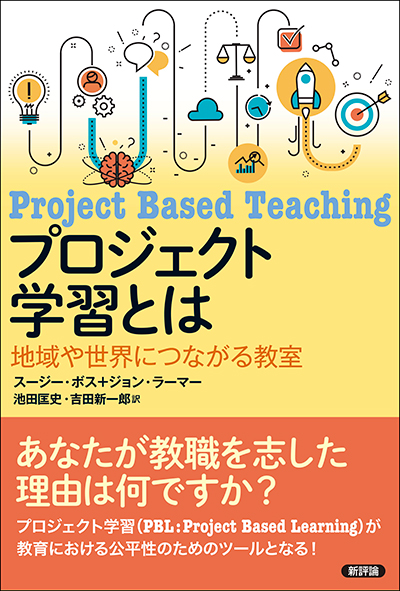
ネット書店で注文
生徒と教師が共に学習計画を立て、何をどう学ぶかを決めていく。人生や社会の課題解決を見据えた学び方の新たなスタンダード。
- 関連ワード
- プロジェクト学習とは 地域や世界につながる教室
- タイトル
- サブタイトル
- 地域や世界につながる教室
- 著者・編者・訳者
- スージー・ボス+ジョン・ラーマー著/池田匡史・吉田新一郎訳
- 発行年月日
- 2021年 6月 3日
- 定価
- 2,970円
- ISBN
- ISBN978-4-7948-1182-0 C0037
- 判型
- 四六判並製
- 頁数
- 384ページ
著者・編者・訳者紹介
著者紹介-
Suzie BOSS(スージー・ボス)
バック教育研究所メンバー、教育コンサルタント。
『ニューヨーク・タイムズ』紙など各種メディアで生活の改善や地域社会の変革に資する教育と学習の力に着目した記事を執筆。
John LARMER(ジョン・ラーマー)
バック教育研究所編集長。
Suzie BOSS(スージー・ボス)
バック教育研究所メンバー、教育コンサルタント。
『ニューヨーク・タイムズ』紙など各種メディアで生活の改善や地域社会の変革に資する教育と学習の力に着目した記事を執筆。
John LARMER(ジョン・ラーマー)
バック教育研究所編集長。
内容
「あなたが教職を志した理由は何ですか?」
この問いかけは、本書が薦める「プロジェクト学習(Project Based Learning、以下PBL)」を学校で推進する役目を担う人物が、教師に投げかけたものです。教員は教壇に立つと、知識やスキルを伝達することに固執するあまり、つい生徒の学びをコントロールしてしまいがちです。PBLは、一つのプロジェクトを通して、自分の人生や社会の課題を解決するスキル、さらには社会のつくり手となるためのスキルを身につけるための、教師と生徒が共につくる学びの文化です。
本書では、PBLの具体的な進め方はもちろん、生徒一人ひとりをいかした学びを実現するための「質の高いPBL」について、数多くの詳細な実践例をもとに紹介しています。
さらに注目すべき点は、PBLが「教育の公平性を実現するためのツール」としての役割を果たすという信念に基づいていることです。そして、教育の公平性に関する信念は、PBLにかかわる多様な生徒同士の関係性だけでなく、教師と生徒との関係性においても貫かれています。
本書に登場する教師たちは、プロジェクトの設計段階から生徒や専門家の意見を積極的に取り入れます。計画段階では、生徒一人ひとりの違いをいかせるような豊富な足場(支援)が用意されています。さらに評価については、評価基準を生徒と一緒につくることもあります。このように、教室にいる教師と生徒が互いの公平性を保ちながら、プロジェクトを通してつくる文化がPBLの学びを最大限に引き出すのです。
PBLは教師と生徒という関係性を越えて、社会のつくり手として共に学ぶことの楽しさと大切さに気づかせてくれます。本書を通じて、教師としての自分が生徒とどんな学びの文化をつくりたいのか、そのためにできることは何かを考えさせられることでしょう。
(協力者 井久保大介)
この問いかけは、本書が薦める「プロジェクト学習(Project Based Learning、以下PBL)」を学校で推進する役目を担う人物が、教師に投げかけたものです。教員は教壇に立つと、知識やスキルを伝達することに固執するあまり、つい生徒の学びをコントロールしてしまいがちです。PBLは、一つのプロジェクトを通して、自分の人生や社会の課題を解決するスキル、さらには社会のつくり手となるためのスキルを身につけるための、教師と生徒が共につくる学びの文化です。
本書では、PBLの具体的な進め方はもちろん、生徒一人ひとりをいかした学びを実現するための「質の高いPBL」について、数多くの詳細な実践例をもとに紹介しています。
さらに注目すべき点は、PBLが「教育の公平性を実現するためのツール」としての役割を果たすという信念に基づいていることです。そして、教育の公平性に関する信念は、PBLにかかわる多様な生徒同士の関係性だけでなく、教師と生徒との関係性においても貫かれています。
本書に登場する教師たちは、プロジェクトの設計段階から生徒や専門家の意見を積極的に取り入れます。計画段階では、生徒一人ひとりの違いをいかせるような豊富な足場(支援)が用意されています。さらに評価については、評価基準を生徒と一緒につくることもあります。このように、教室にいる教師と生徒が互いの公平性を保ちながら、プロジェクトを通してつくる文化がPBLの学びを最大限に引き出すのです。
PBLは教師と生徒という関係性を越えて、社会のつくり手として共に学ぶことの楽しさと大切さに気づかせてくれます。本書を通じて、教師としての自分が生徒とどんな学びの文化をつくりたいのか、そのためにできることは何かを考えさせられることでしょう。
(協力者 井久保大介)
読者からのご感想
学年末、子どもたちに1年間を振り返る文章を書いてもらうのですが、「マラソン大会で順位が上がった」「縄跳びの技が増えた」など、目に見える成果を書いたものがわずかにある程度で、これといって書くことがない=達成感がない子がほとんどです。これは、目標や評価基準を自ら設定するのではなく、教師から与えられているせいだと思われます。子どもたちが自ら具体的・現実的な目標を設定し、教師はその達成を支え、達成度を同級生同士でフィードバックしあう「プロジェクト学習」が求められる所以です。教室でのプロジェクト学習を支援することこそ、まさに授業づくり、学級経営であると感じました。(K.S.)
非常に面白かった。生徒側より教師の側に大きな教育的効果がもたらされると感じた。教員免許更新制度が廃止されたが、その目的には教員の姿勢や価値観のアップデートが含まれていたと思う。しかしこうした制度も上から強制されるのでは意味がなく、単に学校文化の再生産に終わってしまう。プロジェクト学習では、設定したテーマが様々に展開し、その過程で多様な人が関わる。教師が外部からの刺激を受けることで、幸せな学び合いができると思う。(O.H.)
プロジェクト学習という考え方がなぜ大切なのか、その設計はどのようにすればいいのか等、とてもていねいに書かれており、私にとってコーチのような存在の本だ。自分には何ができていて、何ができていないのかもよくわかるし、今後どういうチャレンジをしていくべきかなど、具体的な道筋が見えてくるのもありがたい。読み終えて付箋だらけになってしまったが、これからも再読するたびに書き込みや付箋が増えていきそうです。(M.T.)
非常に面白かった。生徒側より教師の側に大きな教育的効果がもたらされると感じた。教員免許更新制度が廃止されたが、その目的には教員の姿勢や価値観のアップデートが含まれていたと思う。しかしこうした制度も上から強制されるのでは意味がなく、単に学校文化の再生産に終わってしまう。プロジェクト学習では、設定したテーマが様々に展開し、その過程で多様な人が関わる。教師が外部からの刺激を受けることで、幸せな学び合いができると思う。(O.H.)
プロジェクト学習という考え方がなぜ大切なのか、その設計はどのようにすればいいのか等、とてもていねいに書かれており、私にとってコーチのような存在の本だ。自分には何ができていて、何ができていないのかもよくわかるし、今後どういうチャレンジをしていくべきかなど、具体的な道筋が見えてくるのもありがたい。読み終えて付箋だらけになってしまったが、これからも再読するたびに書き込みや付箋が増えていきそうです。(M.T.)




























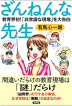


























![[改訂増補版]読書がさらに楽しくなるブッククラブ](https://www.shinhyoron.co.jp/wp/wp-content/uploads/978-4-7948-1137-0-72x106.jpg)